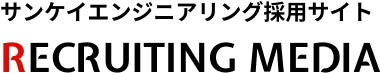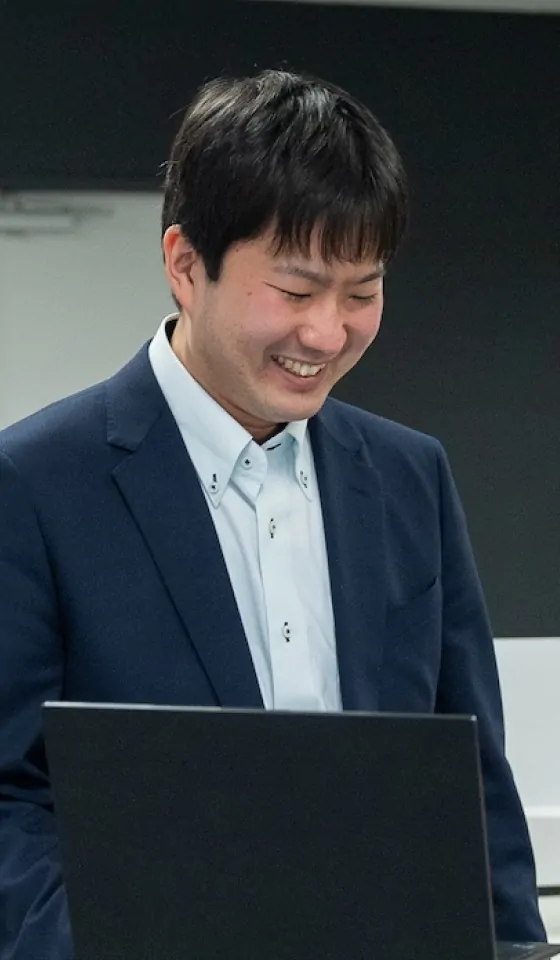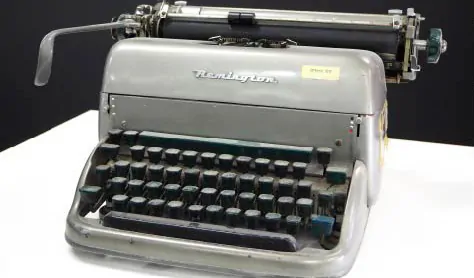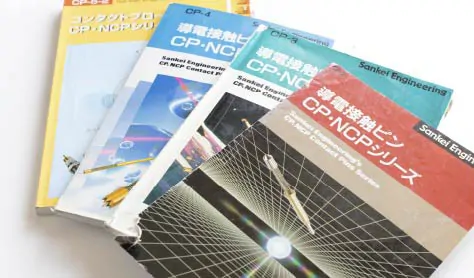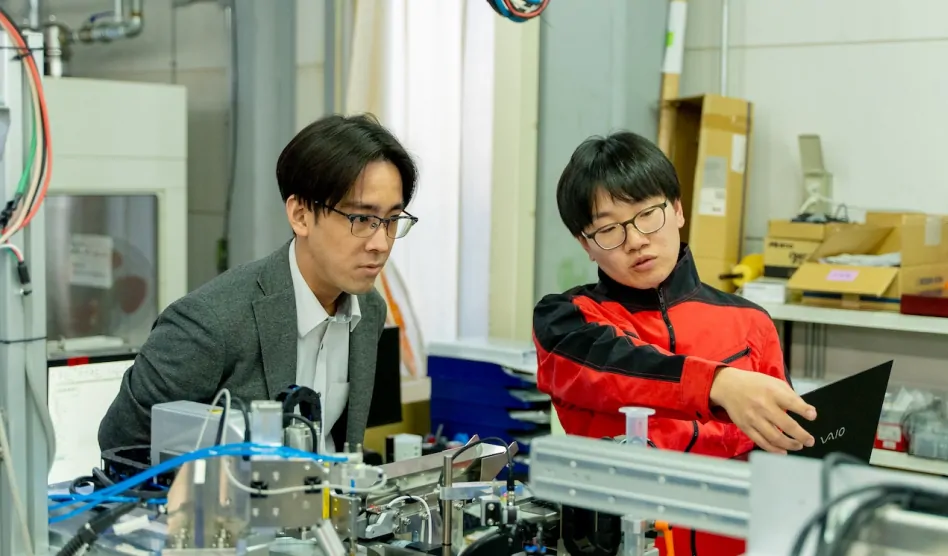「日本のモノづくりを、もっと世界へ」。 多彩なキャリアが導いた、新しい企業文化との出会い

さまざまな業界で経験を重ねてきたS.Y.さんは、現在サンケイエンジニアリングで採用担当を務めています。電気自動車メーカーでのインターンから始まり、人材紹介会社、農業関連の企業、建設業と心のコンパスが指すままに多様なキャリアを歩んできました。
そんなS.Y.さんが、同社の社員を表現する言葉として挙げるのは、「アクティブなオタク」「好奇心モンスター」。中途入社だからこそわかる、ひと味違ったサンケイエンジニアリングを採用担当者の視点からありのままに語ってもらいました。
物語の始まりは、技術を追求する人々との出会いから
――モノづくりへの関心は、どのようなところから始まったのでしょうか。
元々車が好きなんです。ただ一般的な車好きとは少し違って、私の場合は「メカ」の切り口からの車好き。「車のエンジンの中身がどうなっているか」「足回りの素材は何を使っているのか」といった技術的な部分や、「どういう意図でこのデザインになっているのか」「この構造にするとどのような違いが生まれるのだろうか」といった設計・構造面に非常に興味があったんですね。
そんななか出会ったのがGLMという電気自動車メーカーでした。大学生のときにたまたま大阪の梅田へ遊びに行った際に、展示されていたスーパーカーのようなEV車と出会いました。「こんな面白い車を誰が作っているんだろう」と、すぐにFacebookで社長を探して熱烈なラブレターを送り、そこからインターンが始まりました。
GLMには大手自動車メーカーなどでキャリアを積んだ、歴戦のエンジニアたちが集まっていました。「やりたい・実現したいモノづくり」や「ユーザーに感じてほしい楽しみ・喜びを伝える」ために、まるでわが子を育てるように製品を開発していく。そんなエンジニアの世界を知って、さらにモノづくりに魅せられていきました。
その後、大学の卒業が決まり就職を考える時期に差し掛かったときに、GLMへの入社を強く志望していた私は、GLMの社長に直接相談しました。すると社長から「他所の窯の飯を食って(一度外の世界を見て)、力をつけてこい」と言われ、結果的に入社できませんでした。いろいろな想いはありましたが、これをきっかけに、ほかの企業や事業にも目を向けはじめました。
結局、入社したのは運動部に所属する学生に特化した新卒人材紹介会社でした。当初の志望とは異なる業界でしたが、学びもたくさんあり、約1年間勤めました。とはいえ、やはりモノづくりへの想いが捨てきれず、転職を決意しました。その後は農業や建設業など、メーカーではないモノづくり業界を数社経験しました。そこでは、農家や職人の方が、GLMで出会ったエンジニアと同じように、「やりたい・実現したいモノづくり」「ユーザーに感じてほしい楽しみ・喜びを伝える」ためにわが子のようにモノを作っていく現場を知りました。
こうした経験を重ねるうちに「日本のモノづくり」というのは相当レベルが高く、世界に誇れるものだという実感が得られたように思います。この実感は、今働いているサンケイエンジニアリングに入社するきっかけのひとつにもなっています。
本質を見極める文化が育む、新しい働き方
――その後、サンケイエンジニアリングに入社を決めた理由を教えてください。
当時32歳で、「転職市場的にいろいろ選べる最後のチャンスかな」とこれまでのキャリアにない大手企業にもエントリーしたものの、心から納得できる求人には出会いませんでした。スカウトサービスを利用していたのですが、日々膨大に届く「年収〇〇〇万円確約!」「入社直後からマネジメント層」などのスカウトにもピンと来ていませんでした。
そんななかで目に留まったのが、「日本の中小製造業を世界の中核へ」というミッションを掲げるサンケイエンジニアリングです。すごく良いチャレンジだと思いましたし、「絶対できる!やってみたい」というのが最初の印象でした。その一方で「具体的にどういうことをしたいのかがわからない」という思いもありました(笑)。
幸いスカウトをいただいていたので、カジュアル面談からスタートすることができました。そこから面談や会社見学などを通じて「面白い会社だな」「ここなら自分一人では成し得ないチャレンジができそう」という思いが募り、入社を決めました。
――中途で入社して、これまでの企業とどのような違いを感じましたか。
最も印象的だったのは、仕事への向き合い方です。「仕事に必要なことなら、9時から17時の間にやりきる」という考えが浸透していると感じました。アウトプットの質を高めるために本当に必要なことを見極めて、上席や周囲のメンバーと「これ本当に必要だよね」という要素を確認してから効率的に動く組織です。例えば一般的な企業では必要なことを見極めるためのテクニックやノウハウを朝活で学んだり、業務時間外に必要なことの洗い出しをしたりすることが美徳とされるところもあるでしょう。でもサンケイエンジニアリングでは、そういったことも含めて9時から17時の間にやります。時には朝一ダメ出しされて半日スケジュール作成でつぶれるなんてことも……(苦笑)。でもスケジュールをしっかり組むと午後のアウトプットを高い質で出せるようになります。ゴール(=アウトプット)をイメージしながら逆算し、必要なタスクを洗い出し、優先順位をつけ、予定を立てることの重要性を気付かされました。あるべき姿とやるべきことの本質を常に考えて行動する姿勢が、会社全体に根付いていますね。
これは私にとって大きな転換点でした。これまでの会社では、思いつく限りのことを全部自分でやることが当たり前でした。課題が見えたら、必要性の精査・目標(ゴール)の設定・周囲との確認よりも先に解決に向けて動き出す癖がついていたんです。今は何が本質的に必要なのかを一度立ち止まって考えるようになりました。最近は減ってきましたが、このような他社での経験からくる癖を代表の笠原にも指摘をもらうことが多々ありますね(笑)。これまでの企業ではよしとされていた、自分のなかで“当たり前”になってしまっていたことを考え直す機会が増えました。そのほかにも私の場合は、問題の解決にはつながるものの、誰からもOKが出そうな提案をしてしまっていたんです。笠原に「もっと綺麗な五角形のようなものでなく、1点を尖らせた案をもってきて」と言われたときは、ハッとしましたね。
ほかの社内メンバーとのコミュニケーションの取り方も特徴的です。「基本的にコミュニケーションは取れないもの」というフレーズは社内でしばしば聞こえてきます。疑問に思ったことだけでなく、なんとなく「わかった」と思うことでも「こういうこと?」や「こういうことではないよね?」など角度を変えながらイメージの解像度を上げ、納得いくまで質問し、議論を重ねます。そのように認識と解像度の差分を埋めています。そういったやり取りは長年いるメンバー同士でも行われています。
そのうえで、年齢や学歴などに関係なく、フラットな人間関係が築かれているんです。私も社会人歴3~4年目の若手社員から的確な指摘を受けることがありますし、社歴や経験問わずいろんな社員から学ぶことが多いです。例えば、プロジェクトの進め方やメールの文面などを年齢的には年下のメンバーに壁打ちしてもらうこともあります。時にはたくさんダメだしされることもありますが、そういう環境で気持ちよく働けるかどうかは、この会社で働く上で重要なポイントだと感じています。

「日本の中小製造業を世界の中核へ」その可能性
――採用担当として、どのように会社を伝えていますか。
「物事の本質を追求できる環境」だと伝えています。キラキラとした華やかなキャリアパスは掲げていませんが、目の前の仕事に真摯に向き合ったら、その分きちんと評価されます。また、メンバーは「好奇心モンスター」ばかりです。知らないことや、やったことがないことは、積極的に知りたがるメンバーばかりです。新しいことに抵抗感を持ったり、ネガティブな偏見から入ったりすることもあまりないですね。物事に深い関心をもちつつ、人と話すのも話を聞くのも好き、なんなら自分でもやってみるという姿勢を、「好奇心モンスター」、「アクティブなオタク」などと表現しています。
――「日本の中小製造業を中核へ」というミッションに対して、S.Y.さんにはどのような想いがありますか。
日本の中小製造業を世界に発信するという会社のミッションに、私は強く共感しています。このインタビュー冒頭で話した経験や入社のきっかけでもあります。これに加えて話すとすれば、学生時代のある経験があります。海外の人と話す機会があったとき「日本はどんな国なの?」と聞かれて、うまく答えられませんでした。英語を話すことは練習でできるようになりますが、その当時に肝心な日本の魅力を具体的に語れる材料が、自分の中にあまりにも少なかったんです。
まだまだ経験としては道半ばではありますが、今なら日本のモノづくりの素晴らしさを真っ先に語るでしょう。私は今まで日本の技術力の高さを間近で見てきました。こういった物語をもっと世界に伝えられたらと考えるようになりました。
サンケイエンジニアリングは203X年には「日本の中小製造業を世界の中核へ」という構想の本格始動を目指しています。その実現に向けて私に何ができるのか。今は採用の仕事を担当していますが、それ以外にも現場での製品開発や技術営業など、さまざまな可能性が考えられます。
正直なところ、今の時点で具体的な役割を見定めることは難しいです。ただ、この会社には「必要なことを見極めてから動く」文化があります。その時々で最も必要とされることを見極め、自分にできることを着実に積み重ねていく。そうすることで、日本のものづくりの魅力を世界に伝え、日本のレベルの高いモノづくりを世界に発信できる、そんな存在になれればと思っています。