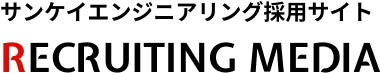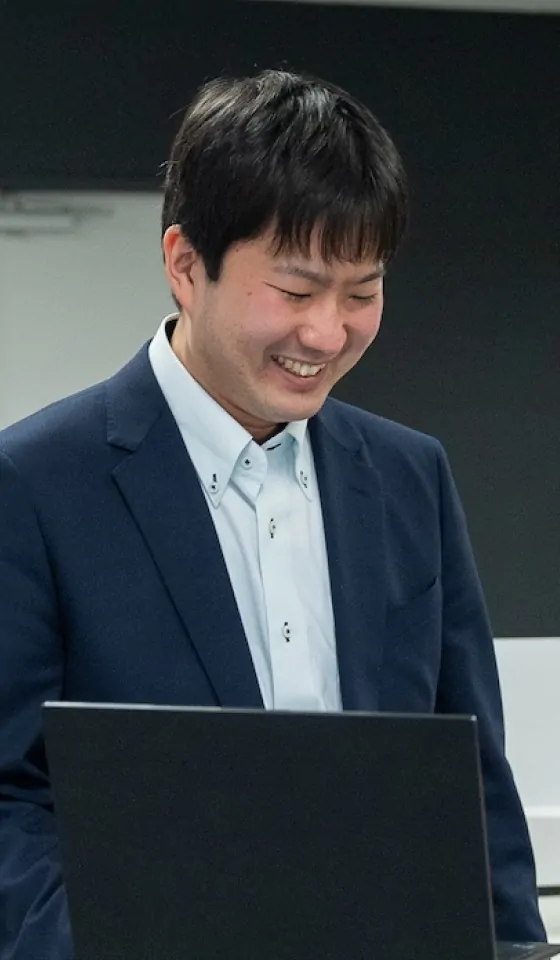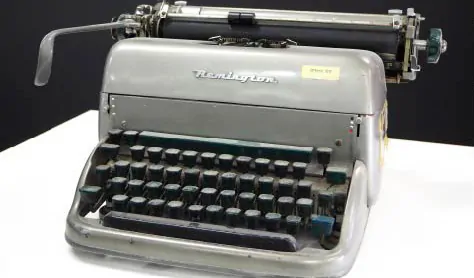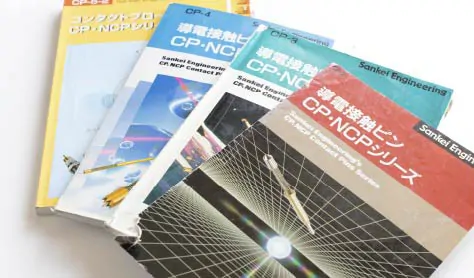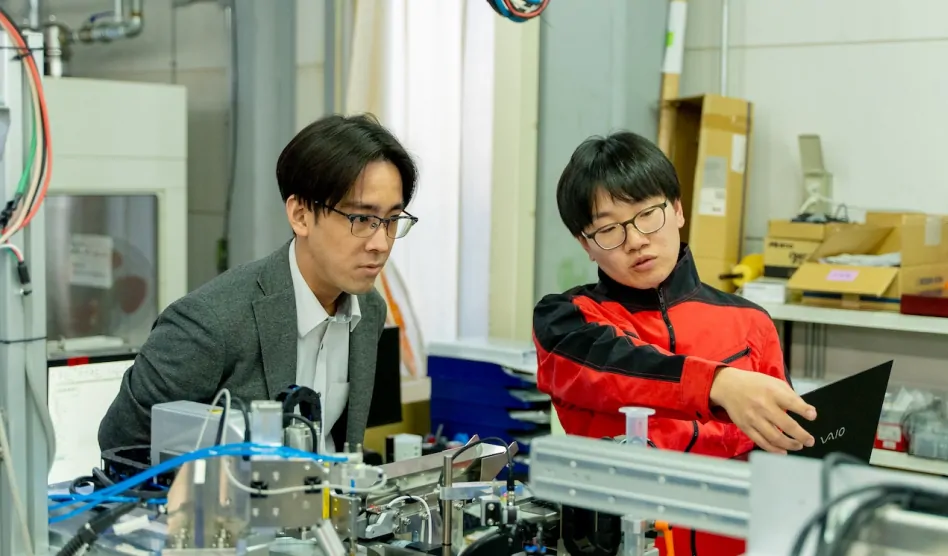「難しい方を選ぶ」が成長の近道。専門外からの挑戦で掴んだキャリア哲学

大学院で社会経済学を専攻していたM.H.さん。サンケイエンジニアリングで社内DX担当として活躍するまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。専門性の掛け合わせと調整力で、製造業特有の複雑な課題に立ち向かうMさんに、キャリア転換の体験談と組織文化の魅力について聞きました。
専門にこだわらず「楽しく働ける環境」を重視
――大学院での研究と、その後の就職活動での企業選びの軸を教えてください。
大学院では社会経済学、特に途上国開発や環境を配慮した経済発展について研究していました。今で言うSDGsに近い分野ですね。
ただ、就職活動では専門知識を活かすことよりも、「楽しく働ける会社か」を重視していました。学問と仕事は別だと考えていたので、シンプルに働く環境が魅力的な会社を探していたんです。
特に重視したのは組織の風通しの良さです。派閥や人間関係のもつれに巻き込まれるのは絶対に嫌だったので、組織的な問題で足を引っ張られるのではなく、自分の努力で解決できる要素が多い環境で働きたいと思っていました。
サンケイエンジニアリングの会社見学で印象的だったのは、「誰に話しかけてもいいですよ」と言われたことです。一般的には、学生がどの社員にも自由に話しかけられる会社はほとんどないので、その点はかなり印象的だったのを覚えています。実際に何人かの社員に質問をして、皆さんが率直に答えてくれたことで、本当に裏表のない会社なんだと確信できました。
製造業×ITの難しさと、信頼関係構築の重要性
――入社後、人事を経てIT担当へと異動したとか。
最初は採用業務のアシスタントをしていたのですが、正直なところ、なかなか芽が出なかったんです。ちょうどその頃、前任のIT担当者が退職することになり、後任として異動することになりました。
IT分野は全くの専門外。特に大変だったのは、IT関連で頼れる人が基本的に社内にいなかったことです。技術や製造に関することなら先輩や上司に聞けるのですが、ITに関しては誰もいない。協力会社やシステム会社に教えてもらったり、あとはひたすら調べたりで、必死に学んでいきました。
今思えば、この経験が自分の成長に大きく影響したと思います。0からプログラミングを学んで実際にシステムを作ったこともありました。技術的な挑戦だけでなく、複数部門間の調整という全く新しいスキルも身につけることができました。当時は「なんでこんな大変なことをしなくちゃいけないんだろう」と思ったこともありましたが、結果的にその時点でのベストを尽くせたと思っています。
――製造業のIT・DXという領域で、どのような課題があったのでしょうか。
実は、弊社のような少量多品種の製造を行う製造現場とITは相性が悪いんです。ITは決まったルールに基づいて処理をして結果を出力するものですから、ある程度条件が定まっていないと運用しにくいのです。しかし、弊社の製造現場は、製品ごとに使用する素材や工具、作業工程が異なるため、条件が製品によってかなり異なってくるんです。加えて現場では常に改善が入るため、一度決まった工程が変わることもよくあります。そういった複雑かつ変化する条件に対して、少ない手数で柔軟に対応できるシステムが必要になります。既存のITツールでは対応しきれないケースがほとんどでした。例えば、10年以上前に導入され、現在も社内で使われている基幹システムがあります。導入してから10年以上経ちますが、変わっていく現場のニーズに合わせて、何回修正したかわからないほど手を加えています。
新しいシステムを現場に導入する際には、どういうルールにするか、どうやって使ってもらうか、現場での導入前トライアルをどう進めるか、異常があった時の報告体制をどうするかなど、細かいところを一つずつ決めながら進めていく必要があります。そのためには、現場との密な連携と信頼関係の構築が不可欠です。
信頼関係構築に必要なのは、まさに一つずつの実績の積み上げでした。どうしたら現場の人に「システム?どれ、使ってやろうか」と思ってもらえるか。そして徐々に「Mがここまで作ったシステムならまぁ大丈夫だろう」といった理解を得られるようになり、「次はこれをやりたいんだけどできる?」と相談を受けるまで、信頼を得ていきました。
――そこからどのような学びを得て、成長したと思いますか。
技術的なスキルはもちろんですが、より本質的な「調整力」が身についたと思います。最初は、考え方や実行方法が全くわからず、上司からも現場からも指摘を受けることが多々ありましたが、その指摘から学び、一つずつ経験を積んでいく中で、導入プロジェクトを進めるための調整能力を身につけていきました。
自分の適性を内省すると、プログラミングなどの技術面よりも、調整や確認の方が苦手だと感じます。でも、逆に言えば、自分にとって難しいことに挑戦した方が、成長につながるはず。今の時代、エンジニアの数は増えていますが、これからの社会で求められる「ITと現場をつなぐ人材」は、それほど多くありません。そこに自分の成長の価値を感じています。

技術者と現場をつなぐ「調整力」でキャリアを描く
――組織文化について、実際に働いてみていかがですか。
入社前に感じた印象は、6年目になった今でも変わりません。他社で働く友人の、人間関係の愚痴めいた話を聞くと、「うちにはそういう問題がないなあ」とありがたさを実感します。
一番大きいのは、個人的な好き嫌いを仕事に持ち込まない文化が根付いていることです。もちろん人間ですから、「この人と仲良くしたい、この人は苦手」という感情はあると思いますが、誰もそれを仕事の場に持ち込まない。よくも悪くも、そういうところにあまり興味がない人が多いように思います。
みんな合理的で、無駄なことはしないし、やるべきことは一生懸命やる。派閥のような組織力学や権力構造を気にする必要がない環境というのは、本当に働きやすいです。類は友を呼ぶと言いますが、そういう人材が自然と集まってくる会社なのかもしれません。
――今後のキャリアビジョンについて教えてください。
現在取り組んでいる社内DXに関しては、まずは製造現場の動きやお金の流れを見える化するところから始まって、最終的にはそのデータを活用した仕組み作りや、社内の文化変革まで含めた、本質的なDXを実現したいと思っています。
将来は、技術を極めるエンジニアになるよりも、IT技術者と現場をつなぐ人材になりたいと考えています。現場が抱える課題に対して必要な技術を見極め、適切な専門を見つけて、プロジェクトをコーディネートする。自分が手を動かすのではなく、調整と確認に徹する方が、できることの幅が増えそうだと感じています。「私がいなかったらこれはできなかった」と思えるような功績を残したいですね。
――就職活動中の学生や、サンケイエンジニアリングに興味をもっている方にメッセージをお願いします。
学生さんに伝えたいのは、「学問と仕事は別でも大丈夫」ということです。私自身、6年間学んだ社会経済学とは全く違う分野で働いていますが、それで良かったと思っています。
専門分野にこだわりすぎると、かえって選択肢を狭めてしまう可能性があります。これからの変化の時代において、一つのスキルだけで生きていくのは難しいでしょうし、複数の柱を持った方が強いはずです。
日本の良いところは、ポテンシャル採用がまだ続いていることです。海外だとITの仕事をしたければ学部からIT系に行かないといけませんが、日本ではその縛りがない。この環境を活かして、新しい分野にチャレンジすることも大切だと思います。
【プロフィール】
イニシャル:M.H.
2020年、大学院修了後に新卒でサンケイエンジニアリング入社。社会経済学専攻から、採用アシスタントを経て現在は社内開発担当(IoT・DX担当)として活躍。製造現場の見える化や業務効率化システムの開発・運用を手がける。専門外分野への挑戦を通じて調整力とマネジメントスキルを磨いている。